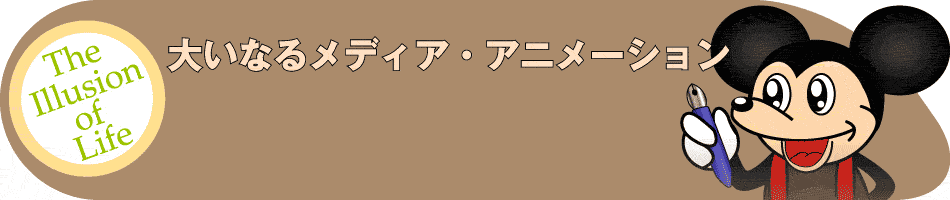ご紹介中の本は、イラストレーターという職業で生計を立てる筆者が、非常に勉強になった本。イラストレーションやアニメーションの勉強では基本ともいえるバイブルです。
徳間書店「生命を吹き込む魔法」
このホームページでは強く印象に残った部分を簡単にご紹介させていただいております。あらすじ未満??実際に書籍を購入されると、きっと一生モノの教科書として活躍してくれると思います。
カテゴリ「アニメーションの技法3」/25
アニメーション基本原則8-1・「副次アクション」前編
ジャンル内の記事リスト
アニメーションの基本原則(アニメーターたちの基本原則9つ)となった手法についてをお伝えしています。
今回はアニメーション基本原則8、「副次アクション」その1。
8番目のアニメーション原則 副次アクション前編
副次アクションとは!?何ぞや?
あるアクションの狙いは、副次的なアクションで強調できることが多いです。
- 悲しみにくれたキャラクターは、顔をそむけつつ涙をぬぐう。
- 気絶から復活したキャラクターは、立ち上がりながら首を振る。
- 取り乱れたキャラクターは、落ち着きを取り戻した時、メガネをかける。
上記の様な主要なアックションを支える動きのことを副次アクションと言います。
副次アクションの一番分かりやすいキャラクターは、ディズニーアニメション制作スタジオのアニメーター、ビル・タイトラ氏のイラスト作品。
「白雪姫」の七人の小人のの中のひとり、グランピー(性格はおこりんぼ)をお風呂に入れるよう他の小人達に指示しながら、大騒ぎするドック(みんなからは先生と呼ばれています)の振り向きざまの体全体のパーツごとのたるみの動きです。
体が上下に飛び跳ねるのがアニメーションでは主要な動きですが、ドック(先生)の混乱は、体とは違うパターンで腕が動くことに 表れています。
そのほか、しゃべるときに頭部が上下するという動きもあります。これらの副次アクションは動きを刺激的にしますが 基本のアクションと対立、ぶつかることは、ありません。
副次アクションは、主要なアクションに対し常に従属的な立場にし なければなりません。副次アクションが、主要なアクションと対立した り、主要なアクションより、目立ったりするする場合は、副次アクション自体がまちがっているか、演出に問題があると言える のです。
これで難しいのは、別々ではありますが、関連しているキャラクターの体の各部をうまく動かすことで、まとまった表現を作ることです。キャラクターの悲しげな表情が主要なアクションになっているときは、涙をぬぐう手の動きは、そのキャラクターの悲しげな表情を支えるよう設計しなければいけません。こぶしで顔を隠してしまうような派手なジェスチャーは問題外!
しかし、動きを抑えすぎると弱々しく、ちまちました感じになり主要なアクションとの関連が、わからなくなってしまうので下限が難しいのです。副次アクションを主要なアクションの特徴にあわせて設計し、それによって表情をきちんと強調できれば、そのカットは 素晴らしいものになるのです!
次回は副次アクション後編です。おたのしみに。
ディズニーアニメーションの歴史はディズニーイラストの歴史でもあります。
これだけの長い間、愛され続けるディズニーキャラクターは、
イラストレーションを考える上での基本となるポイントが満載です。
徳間書店「生命を吹き込む魔法」というバイブル、
実売で1万円前後と若干高価ですが、興味をもたれましたら、
ぜひ手にとってご覧下さい。